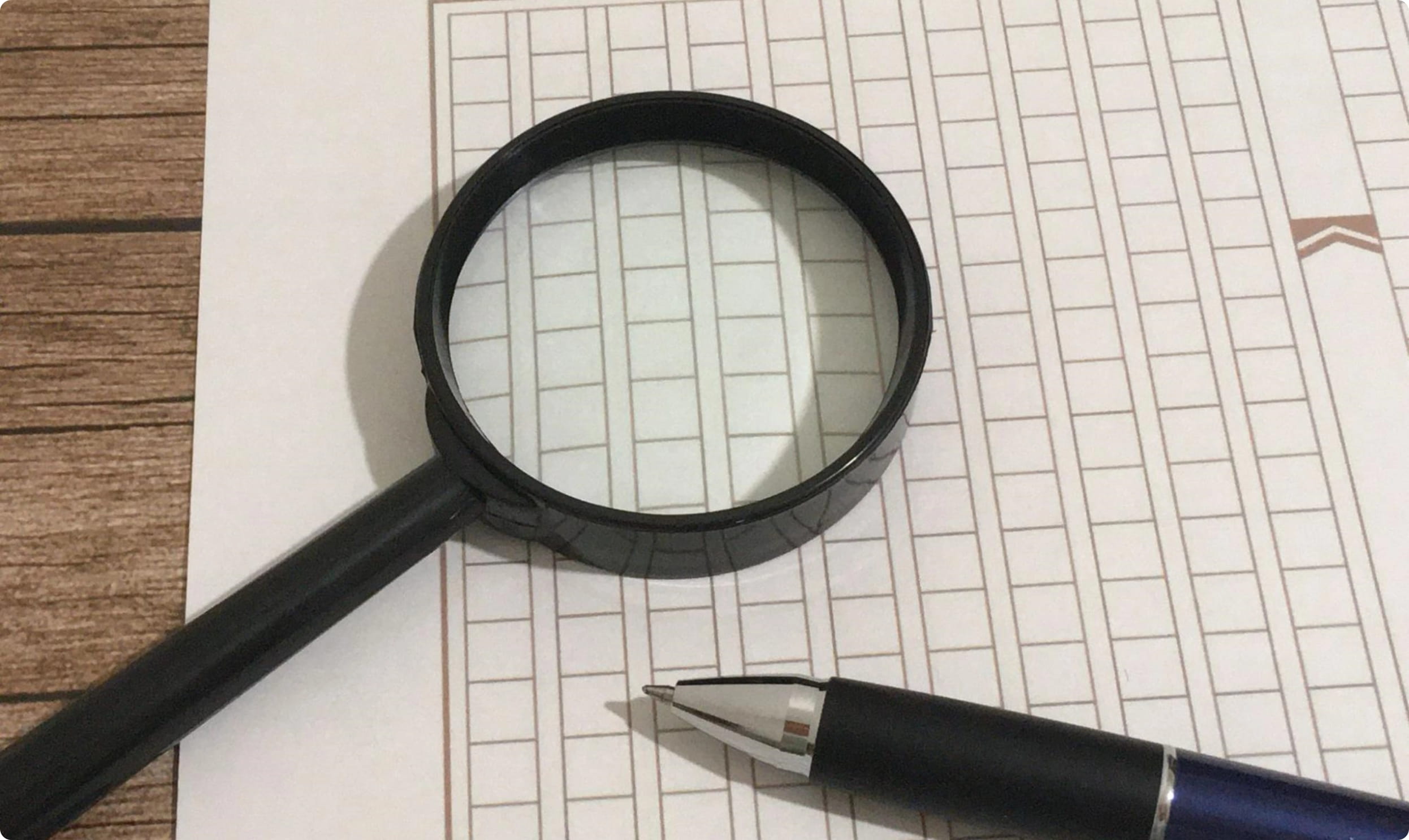学資保険の代わりとしておすすめの教育費の準備方法6選と選び方
2025.04.30
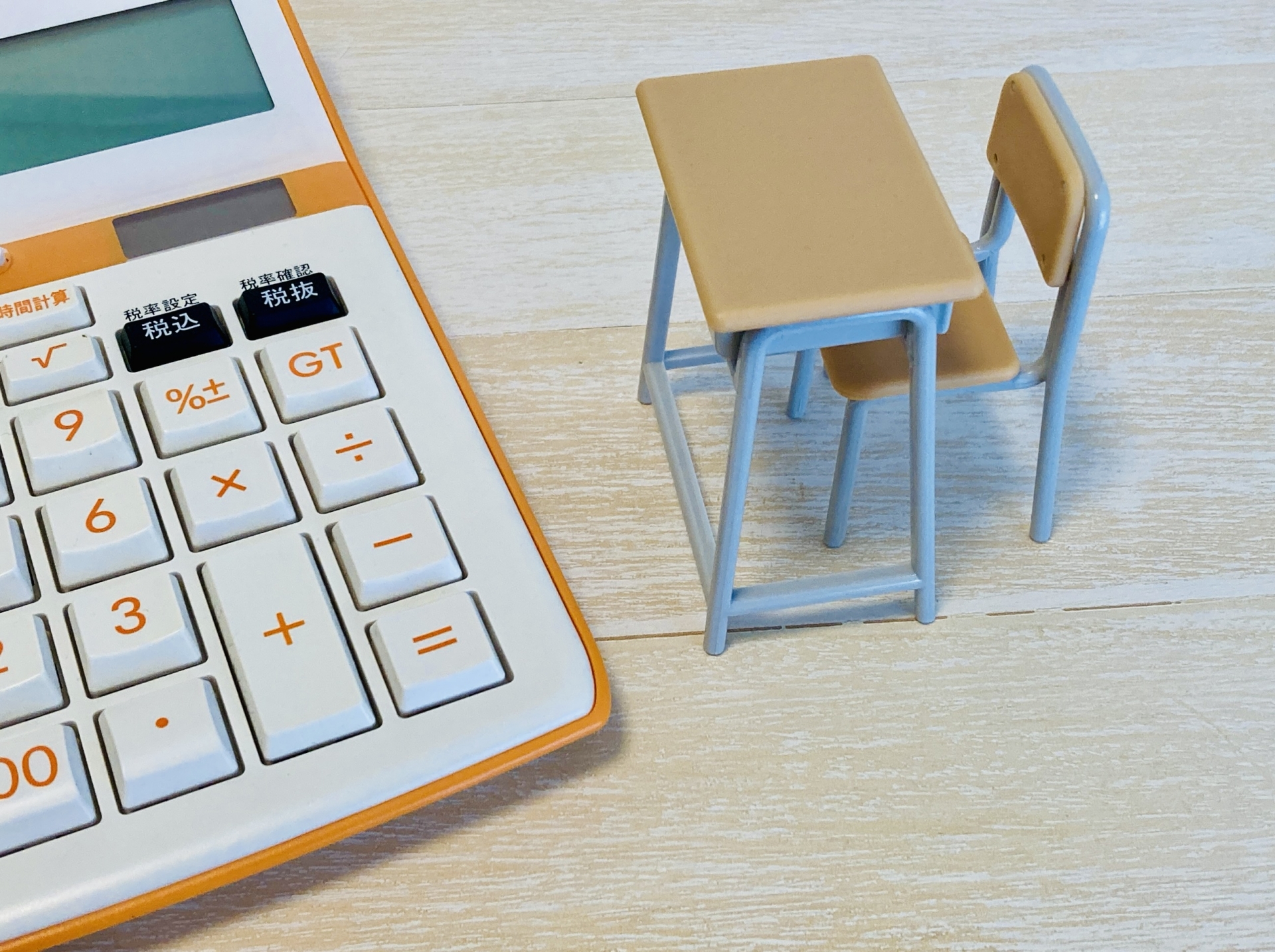
学資保険は、子どもの将来の教育費を計画的に準備するための手段として広く利用されています。しかし、そのメリットとデメリットを理解せずに契約すると、後悔する可能性もあります。
学資保険を検討する際は、その仕組みを理解し、家計や子どもの将来に適した方法を選ぶことが大切です。
この記事では、学資保険の主なメリット・デメリットと、教育資金を準備する他の方法について紹介します。大切な子どもの教育資金を準備するための方法を、ぜひ一緒に考えてみてください。
目次
そもそも学資保険とは?
学資保険は、子どもが将来必要とする教育資金を早めに積み立てていく保険商品です。
保険の契約者(多くの場合、子どもの両親や祖父母)は、一定期間にわたり保険料を支払い、満期を迎えると「満期保険金」や「祝い金」を受け取ることができます。
教育資金を活用し、入学金や授業料、書籍代などの教育費を支払うことができます。そのため、その場で貯蓄から資金を取り崩す必要がなく、計画的に準備したお金を使えます。
学資保険には次のような特徴があります。
| 特徴 | 内容 |
| 貯蓄 | 満期の設定により計画的に積み立てられる 家計からのやりくりが不要で自動的に積み立てられる |
| 保障 | 保険の契約者が、万が一の事態に陥った際の死亡保障 保険の契約者が、万が一の事態に陥った際の払込免除 その他の保障 |
| 税制優遇 | 生命保険料控除(所得税・住民税) |
学資保険は、教育資金を計画的に準備する手段です。貯蓄では目標金額まで貯められない可能性があるため、確実に資金を確保したい方に適しています。
学資保険にはさまざまな商品があり、特約を選んでカスタマイズすることも可能です。各家庭の状況に合った選択が重要となります。
学資保険に加入するメリット
学資保険に加入するメリットは次のとおりです。
【貯蓄性】
給与の中から教育資金だけを確保しようとしても、計画どおりに貯められないことがあります。
そのようなときでも学資保険に加入しておけば、半強制的に月々の保険料が引き落とされるため、「つい他の目的に使ってしまう」という事態が防げます。計画的に貯蓄できるため、貯蓄が苦手な方にも適した方法といえます。
【保障機能】
学資保険は生命保険の一種です。契約者に万が一の事態が発生した場合、保険金が支払われるほか、死亡後の保険料の払い込みが免除される仕組みになっています。そのため、被保険者である子どもにとっても安心です。
また、契約者が死亡・高度障害状態に陥った際に、すでに支払い終えた保険料の相当額が「死亡給付金」として支払われます。払い終えたお金が戻るため、貯蓄性の高い保険商品といえます。
【生命保険料控除】
生命保険料控除とは、その年(1月1日~12月31日)に保険会社へ支払った保険料の一部を、所得から差し引くことができる制度です。
所得控除の一種で、所得税や住民税が軽減されるため、税負担を抑えやすいというメリットがあります。
学資保険に加入するデメリット
次に、学資保険に加入するデメリットをみていきましょう。
【保険料の負担】
学資保険は毎月一定金額を保険料として支払っていく保険商品です。
家計が苦しいときでも保険料を支払わなければならず、どうしても支払えないときは契約者貸付制度の利用や保険料の見直し(減額)を検討しなければなりません。
それでも支払いが難しい場合は中途解約となりますが、途中で解約すると、支払った保険料が全額戻らないリスクがあります。
【流動性の低さ】
払い終えた保険料は、事前に定めた契約期間がすべて満了するまで自由に引き出せないシステムです。
そのため、「ある程度お金が貯まったのでそろそろ使いたい」といった自由な使い方ができず、中途解約では返戻率が低く設定されているため、急な出費や解約に対応できません。
【固定金利】
学資保険にはさまざまな種類があるものの、多くの商品は固定金利のため、契約時に設定した利率が満期まで適用されます。
固定金利は市場の動向や景気変動に左右されない一方、金利上昇による恩恵も受けられません。
期待したほどのリターンが得られないうえ、社会情勢によってはインフレの影響を受け、元本割れのリスクも生じます。
学資保険の代わりになるおすすめの教育資金の準備方法
学資保険の代わりに教育資金を準備する方法として、「低解約返戻金型終身保険」「外貨建て終身保険」「個人年金保険」「変額保険」「預貯金」「投資信託」などがあります。
それぞれの特徴やメリットについて、詳しく見ていきましょう。
低解約返戻型終身保険
低解約返戻金型終身保険は、死亡や高度障害に対する保障が一生涯続く保険商品です。
払込期間中に解約すると、返戻金は支払った保険料の約70%に抑えられます。
中途解約では返戻金が少なくなりますが、払込期間が満了すると返戻率が上がり、100%を超えることもあります。
低解約返戻金型終身保険のメリットは次のとおりです。
- 解約返戻金は低くなるが保険料が割安になる
- 契約者の死亡や高度障害状態が保障される
- 払込期間満了後の返戻金の割合が高く設定されている
払込期間の種類は3つに分けられます。
| 名称 | 払込期間の決まり方 |
| 歳満了 | 被保険者の年齢を60歳や65歳のように決めて、その年齢まで払込期間が発生するもの |
| 年満了 | 「10年」「20年」と年数で払込期間が決まるもの |
| 終身払い | 払込期間を特に定めずに被保険者が死亡するまで保険料を払い込む方法(終身払い)から選べるもの |
保険商品のため、各家庭のニーズに合わせて必要な保障を特約として付帯することができます。
外貨建て終身保険
外貨建て終身保険は、米ドルやユーロなどの外貨で支払った保険料を外貨で受け取れるシステムの終身保険です。
円安時でも、価値の高い外貨で運用できるため、一定の利益を得られます。保険期間は一生涯で、日本円よりも金利の高い通貨を選ぶと高利回りが期待できます。
外貨建て終身保険のメリットは次のとおりです。
- 円建ての保険よりも予定利率が高い
- ドル資産やユーロ資産に投資できる
- 円資産よりも成長が期待できる
米ドルは予定利率の高さから選ばれやすい傾向にあり、円建ての終身保険よりも高い利率で運用できる点がメリットです。
一方、外国為替による為替レートの変動リスクや為替手数料の発生に注意が必要です。万が一為替相場が円高へ進んでいる場合、円換算したときに支払った保険料の総額が下回ってしまうリスクがあります。
そのような状況で満期を迎えると、支払った保険料の100%に満たない金額しか戻らず、元本割れのリスクがあります。
個人年金保険
個人年金保険とは、毎月支払った保険料を将来、年金として受け取る保険商品です。
老後資金を蓄えるための保険であり、公的年金とは別に年金を準備したい場合に適しています。この保険商品を学資保険の代わりにする場合、契約時に満期(契約者の年齢)を決めて、その年齢まで保険料を払い込みます。
個人年金保険はドル建てにすることも可能ですが、必ずしもドルやユーロで運用する必要はありません。
個人年金保険のメリットは次のとおりです。
- 子どもの成長に合わせて満期を設定できる
- 健康状態の告知や医師の診査が不要
- 満了後は年金として受け取れる
子どもの教育資金がかかるタイミングに満期を設定しておけば、満期に必要なお金を受け取れます。健康状態の告知・医師の診査が不要なものも多く、健康状態に不安がある方や既往症のある方でも選びやすい保険です。
払込期間が満了した後は、年金として受け取れます。教育資金として活用するだけでなく、契約者の年金としても利用できるため、二世代にわたって備えることが可能です。
変額保険
変額保険とは、死亡保障と投資信託をセットにした保険商品です。
契約者が支払う保険料は、投資信託などの金融商品で運用され、運用成果に応じて保険金や解約返戻金の額が変動します。そのため、「変額」と呼ばれます。
プロによる運用によってインフレーションに強いという特徴もありますが、一般的な保険商品よりもやや仕組みが難しいため、内容をよく理解して契約する必要があります。
変額保険のメリットは次のとおりです。
- 投資連動型の保険商品である
- 高いリターンが得られる可能性
- 投資対象が変更できる変額保険もある
投資を前提とした保険商品のため、ハイリスク・ハイリターンが大きな特徴です。投資が順調であれば預貯金や定額保険よりもリターンが大きくなりますが、運用成績が悪化すると保険金額が減少するといったリスクも伴います。
一部の変額保険は、資産配分(※)が変更できます。価格や金利の変動リスクはありますが、市場の動向を見て資産を配分し、資産の保全や収益の獲得を目指せます。
※資産配分:変額保険の特別勘定資産をどの金融商品に振り分けるかを指す。
預貯金
預貯金は、給与やその他の収入・利益を教育資金として蓄える方法です。保険に加入する必要がなく、元本割れのリスクや心配もないためもっとも一般的な方法といえます。
普通預金は自由に出し入れできる預金の一種で、定期預金や財形貯蓄は毎月一定額を積み立てる方法です。
積み立ての有無にかかわらず、預貯金だけで教育資金を貯める場合は計画性や保障がつかないといった点に注意が必要です。
預貯金のメリットは次のとおりです。
- 契約や投資の必要がない
- 貯蓄の配分を自由に変更できる
- 家族や自治体からの支援を受けやすい
預貯金は、子どもの親や祖父母などの保護者が自由に貯蓄することができます。保険商品は契約者を決めて、その契約者が責任をもって支払いを続けなくてはなりませんが、預貯金は家族全員で協力してお金を出し合うことができます。
十分な収入があれば、無理に投資を行う必要はありません。必要な金額を適切なタイミングで準備できれば、教育資金の積み立ては不要です。
投資信託
投資信託は、投資家から集めたお金をプロが運用して利益を稼ぎ、得られた利益を分配する金融商品です。
利用者自身でお金を運用する必要がなく、株式や不動産に詳しい知識がなくても利益を得られる仕組みです。
ただし、銀行や証券会社で商品を購入する必要があるため、投資対象への理解は必要です。「投資に興味があり、教育資金を貯めていきたいが、自分で運用するのは不安がある」という方に適しています。
投資信託には、次のようなメリットがあります。
- 専門家によって運用される
- ハイリターンが期待できる
- 新NISAが活用できる
株式や債券といった金融商品の特徴を理解し、投資に求められる知識や手法を身につけるのは難しいものです。しかし、投資信託なら知識と経験をもつプロが直接運用します。
投資対象は幅広く、学資保険よりも利益を出しやすい点が特長です。新NISAを活用するなどして、効率良く教育資金が準備できます。
投資信託は保険商品ではないため、売却するタイミングに制限はありません。保有する投資信託の一部のみ売却できるため、流動性や柔軟性の高さが魅力的です。
教育資金に関する支援制度
教育資金に関する支援制度は、学資保険やその他の方法とは別に、お子さんの将来に備えるための支援です。
「児童手当」「高等教育の修学支援新制度」「高等学校等就学支援制度」「奨学金制度」「(国の)教育ローン」の5つを詳しくみていきましょう。
児童手当
児童手当とは、0~18歳の子どもを養育している保護者に支給される制度です。
0~3歳未満、3~18歳までの2つの区分と、子どもの人数によって支給額が決まります。2月から12月まで、年6回に分けて支給が決定した月額が振り込まれます。
手当は、子どもを養育する家庭の生活安定や子どもの進学・学業に活用されるため、そのまま教育資金として貯蓄できます。
高等教育の修学支援新制度
高等教育の修学支援制度とは、進学を希望する子どもが大学・短期大学・高等専門学校・専門学校へ進学できるよう、授業料・入学金の免除や減額、返還不要の給付型奨学金を支援する制度です。
2020年4月に開始された制度で、「世帯収入や資産の要件を満たしている」「進学先で学ぶ意欲がある」などの条件を、レポートや成績で総合的に評価したうえで利用できます。
世帯収入に応じて4段階の基準が適用され、支援の範囲が変わります。2024年からは新たに、世帯年収600万円以下の家庭も対象となりました。
高等学校等就学支援制度
高等学校等就学支援制度とは、家庭環境や公立・私立にかかわらず、国が学費の一部を負担する制度です。
国が各都道府県に就学支援金の費用を交付し、都道府県が学校へ就学支援金を支給します。学校側は、制度の利用を申請した生徒の授業料に就学支援金を充てるため、授業料の負担が軽減されます。
受給資格は、日本国内の高等学校・高等専門学校・専修学校等に在籍する学生です。ただし、世帯年収が910万円を超える場合、高等学校等をすでに卒業・修了している場合、在学期間が一定の期間を超えている場合は対象外となります。
ただし、世帯年収の要件は親が離婚している場合や入学者が20歳を超えている場合などで異なるため、詳しくは最寄りの役所・役場や通学中の学校へお問い合わせください。
奨学金制度
奨学金制度とは、経済的または家庭の理由で進学が難しい学生に対し、学費や生活費を給付(給付型)または貸与する(貸与型)制度です。
大学・地方公共団体・独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO)等が実施している奨学金制度は「公的奨学金」と呼ばれ、学校・企業・育英団体が実施する制度は「民間奨学金」と区別されています。
奨学金の給付や貸与を受けるには、学力や家計に関する基準を満たす必要があります。さらに、貸与型の奨学金は利子がつかない「第一種奨学金」と、利子が発生する「第二種奨学金」に分かれるため、どちらに該当するか確認が必要です。
国の教育ローン
国の教育ローンとは、「教育一般貸付」という名称で提供されている制度です。
上限350万円(※)まで借り入れることができる制度で、固定金利も低く設定されています。日本学生支援機構の奨学金と併用したり、さまざまな教育機関への進学や用途に対応したりと、柔軟に借入金を利用できます。
奨学金は子どもが利用しますが、国の教育ローンは保護者が借り入れ、通学や進学、海外留学の費用として活用できます。
金利は固定されているため、長期の返済でも対応しやすく、計画的に返済できます。
※2025年1月時点
教育資金はどのくらい必要?
子どもにかかる教育資金は、公立か私立か、大学へ進学するかなどの進路によって変わります。
文部科学省「令和3年度子どもの学習費調査」によれば、幼稚園~大学までの公立と私立にかかる教育費は次のとおりです。
| 教育費/年 | 公立 | 私立 |
| 幼稚園 | 16万5,126円 | 30万8,909円 |
| 小学校 | 35万2,566円 | 166万6,949円 |
| 中学校 | 53万8,799円 | 143万6,353円 |
| 高校 | 51万2,971円 | 105万4,444円 |
| 大学 | 92万7,668円 | 117万6,894円 |
上記は目安であり、授業料が引き上げられると公立でも一定の費用がかかります。
もっとも教育費がかかるのは大学といわれていますが、大学修了後に大学院や海外留学、国内交換留学を選択すると、さらに教育費がかかります。
高校を卒業するまでにかかる費用
幼稚園〜大学までの公立と私立にかかる教育費の例を踏まえると、高校を卒業するまでにかかる費用は次のように計算できます。
- すべて公立の場合(高校まで):560万958円
- すべて私立の場合(高校まで):1809万1,903円
※幼稚園は2年保育の場合
すべて公立の場合でも500万円以上の費用がかかるため、計画的に準備することが重要です。
幼稚園を3年保育にした場合や、公立から私立の学校へ進学した場合は、560万958円よりも費用がかかります。進路をよく考え、貯蓄や保険・ローンの活用を検討しましょう。
大学進学でかかる費用
大学の進学にかかる費用は、次のとおりです。
| 教育費/年 | 公立 | 私立 |
| 大学 | 92万7,668円 | 117万6,894円 |
※大学は授業料と入学金の合計
大学の修業年限は通常4年ですが、一部の学部では5年制や6年制の場合もあります。留年すると在籍期間が延び、その分の学費が追加で必要になります。
また、幼稚園〜大学までの公立と私立にかかる教育費の例から、大学を卒業するまでにかかる費用は次のように計算できます。
- すべて公立の場合(大学まで):931万1,630円
- すべて私立の場合(大学まで):2279万9,479円
※幼稚園は2年保育の場合
費用は目安のため、学部や学ぶ内容によっては教育費が前後します。大学生活では授業料だけではなく生活費やその他の費用も必要になるため、計画的に貯蓄をしておきましょう。
学資保険を選ぶか代わりになるものを選ぶか決める際のポイント
子どもの教育資金を検討するとき、学資保険の代わりになるものをどのように選ぶかによって、その後の家計管理が変わってきます。
学資保険とそれ以外の選択肢のどちらを選ぶか悩んだときは、次のポイントを参考にしてください。
| 注目点 | 考慮するポイント |
| 家計の状況 | 給与などの収入・学資保険の保険金額が予算内に収まるか |
| 保障内容 | 契約者の万が一の事態に備えられるか・満期の設定時期・不要な保障内容が含まれていないか |
| 返戻率 | (100%を基準に)どの程度の割合で払込保険料が戻るか・元本割れのリスクの有無 |
| 手数料・コスト | 運用コスト・手数料・初期費用の有無と金額 |
| 柔軟性・流動性 | 中途解約の可否・保険料の金額変更や一時払いの可否・その他運用上の制限 |
| 信頼性 | 金融商品としての信頼性・保険会社の信頼性 |
学資保険を選ぶか迷ったときは、家計の状況を第一に考えます。契約者の年齢やお子さんの年齢も考え、学資保険に加入できる状態かどうかを判断しましょう。
学資保険は、多くの場合子どもの年齢が0~3歳の間に加入することを想定していますが、幼稚園以降~6~7歳ごろまで加入できる商品もあります。ただし、加入時期が遅れるほど払込期間が短くなるため、保険料が割高になるケースも想定しなければなりません。
返戻率は商品によって異なり、中途解約の際の返戻率も商品ごとに設定されています。どの方法を選ぶか悩んだときは、保険のプロや金融商品・家計管理の専門家に相談するのがよいでしょう。
学資保険の代わりを選ぶ場合はいくつかのポイントを確認
今回は、学資保険の代わりにできるおすすめの方法や考慮したいポイントを紹介しました。
学資保険とその他の選択肢を比較する際は、「計画的に貯蓄したいか」「契約者のリスクに備えるべきか」「資金を増やしてリターンを狙いたいか」などの観点から検討することが重要です。
教育資金の確保は各家庭にとって重要な課題です。投資や預貯金、支援制度や奨学金などを組み合わせることで、効率的に資金を準備できます。
学資保険は柔軟性に乏しいといわれていますが、一方で教育費の貯蓄を確実に行えます。家計の状況や将来の進路を総合的に判断し、将来に備えましょう。
お客様の声

親身になって必要な
保険を教えてくれました!
30代男性保険見直し生命保険
30代に入り家族も増え、真剣に将来のことを考え始めたところでした。そんな時、友人に勧められ訪れました。私のライフステージに合わせた生命保険の提案をしてもらえました。特に子供の教育資金や将来のリスク管理に関するアドバイスが具体的で、非常に参考になりました。ほけんスマイルの方々は知識が豊富で、安心して相談に乗ってもらえる環境が整っていました。今後も家族の安全を守るために、ほけんスマイルと長く関わっていくつもりです。

新規で生命保険に加入して、
未来への安心を手に入れました!
20代女性新規加入生命保険
保険のことは難しくてよくわからなかったのですが、ほけんスマイルのスタッフさんがとても親身になってくれて、自分にとって最適な保険プランを提案してくれました。
私でも理解しやすいように、細かいポイントまで説明してくれたので、安心して加入することができました。これで万が一の時も安心です。

医療保険への新規加入で
安心を得ました!
30代女性保険見直し医療保険
医療保険を見直したいと思いつつ、どの代理店に相談すれば良いのか分からなかったのですが、知人に勧められたほけんスマイルで相談して大正解でした。
30代という節目での見直しに対して、具体的で実用的なアドバイスを受けることができ、保険内容も大幅に改善されました。