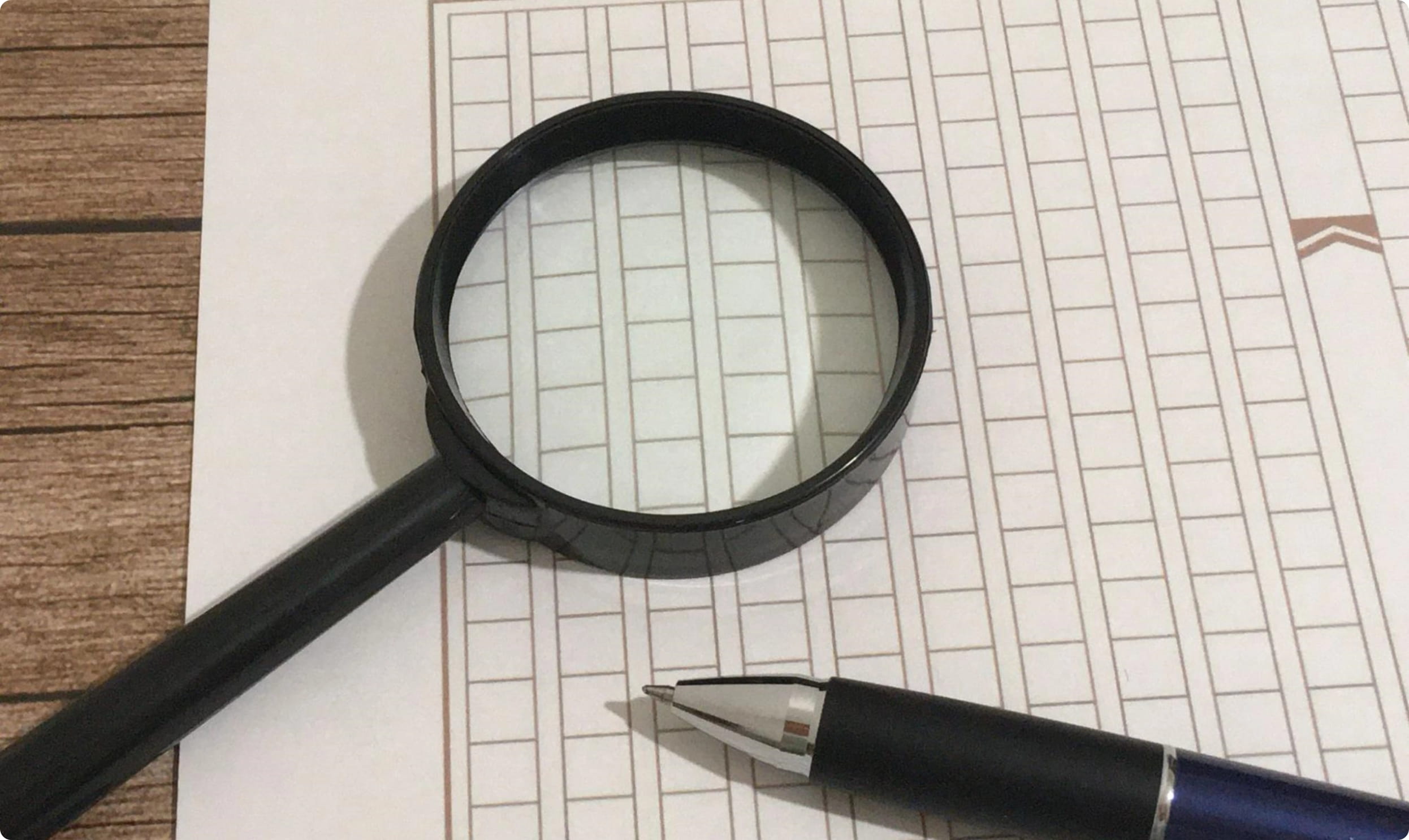医療保険の選び方とは?注目したいポイントと保険商品選びの流れ
2025.04.30

医療保険に加入しようと調べたものの、商品の多さに驚いた方もいるのではないでしょうか。
そこで「種類が多すぎて選べない」「自分に合った保険がわからない」と困っている方のため、どのようなポイントに注目すればよいのか、選び方のコツを紹介します。
この記事を読めば、確認すべきポイントや保険選びの流れがわかるので、ぜひ参考にしてください。
目次
公的医療保険と民間の医療保険の違い
医療保険には、公的医療保険と民間の医療保険の2種類があります。
まず、日本では「国民皆保険制度」と呼ばれる制度によって、すべての人が公的医療保険に加入するのが義務です。
全員が保険料を支払うことにより、お互いの保険料負担を軽減することを目的としてこの制度が作られました。
一方、必要な方が任意で加入するのが、民間の医療保険です。
公的医療保険への加入は義務であるため、民間の医療保険に加入しても公的医療保険には必ず加入しなければなりません。
公的医療保険には、被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の3種類があります。
被用者保険は会社員や公務員、その家族を対象にした健康保険であり、組合管掌健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、共済組合の4種類です。
次に市区町村によって運営されている医療費制度が国民健康保険で、自営業の方や農業を営んでいる方、無職の人などが対象となります。
後期高齢者医療制度は、75歳以上もしくは65歳以上で障害を持つ高齢者を対象とした公的医療保険制度です。
これらの公的医療保険制度を利用することにより、安価で質の高い医療を受けられます。
しかし、公的医療保険だけでは、すべてのリスクに対応するのは難しいのが現状です。
治療によっては、高額な治療費がかかってしまうものもあるためです。
そういった場合に役立つものとして民間の医療保険があります。
保険料はかかりますが、将来に備えたい方に選ばれています。
公的医療保険の対象外となる費用の例
病気やケガの治療費すべてが、公的医療保険の対象になるわけではありません。
たとえば、以下のようなものは対象外です。
【対象外となる費用】
- 差額ベッド代
- 入院中の日用品費と雑費
- 見舞いに来る家族の交通費・食事代
- 正常分娩
- 自由診療
- その他
差額ベッド代とは、自ら希望して個室に入院した場合や、3~4人部屋、2人部屋を利用した場合にかかる費用のことをいいます。
病院側から案内された6人部屋などに入院する場合、差額ベッド代はかかりません。
差額ベッド代が発生する場合は全額自己負担となり、個室部屋に近いほど高くなります。
自由診療とは、公的医療保険を適用せずに受ける治療のことです。
たとえば、抗がん剤薬の中にも公的医療保険の対象外となるものがあります。
民間の医療保険を選ぶときに確認すべきポイント
公的医療保険ではカバーできない分に備えたいと考えているのであれば、民間の医療保険への加入を検討するとよいでしょう。
ただし、保険の種類が多いため、どれを選ぶべきか迷うこともあります。
そこで、保険の選び方として、以下の7つのポイントを確認しておいてください。
ポイント①保険期間
保険の選び方として特に重要なのが、保険期間です。
保険期間とは、保険契約が続く期間のことをいいます。
保険期間は、大きく分けると「終身タイプ」と「定期タイプ」の2種類です。
終身タイプとは、一生涯保障が続く保険のことをいいます。
保険料は保障内容を変更しなければ原則生涯一定です。
定期タイプとは、あらかじめ定められた期間のみ保障されるタイプのことをいいます。
商品によっては保障期間が満了した際に契約を更新できるものもあるため、そのタイミングでの乗り換えも検討しやすくなるでしょう。
終身タイプと異なり、更新する際はそのときの年齢で再度保険料が計算されることになります。
そのため、更新を繰り返すたびに保険料が上がります。
自身の場合はどちらが向いていそうか検討しましょう。
ポイント②入院時の保障内容
入院が必要になったときのために備えておきたい方は、入院時の保障内容をよくチェックしてみてください。
入院給付金と呼ばれるものがあり、契約時に設定した金額を1日あたり5,000円、1万円などの形で受け取れます。
支払い限度が決まっているので、何日を上限としているかも確認しておかなければなりません。
60日の上限を設定しているものが主流ではありますが、それよりも長い日数や短い日数を設定しているものもあります。
入院中は日用品や備品の購入費用なども含めてさまざまな費用がかかることになるので、どの程度あれば助かるのかを考えておきましょう。
公益財団法人 生命保険文化センターが行った調査によると、入院時の一日あたりの自己負担費用の分布で特に多いのは10,000円~15,000円未満でした。
ついで20,000~30,000円未満となります。
また、自己負担費用の平均は19.8万円です。(※)
すべての費用を民間の医療保険で補う必要はありません。しかし、貯金が少なく保険に頼る必要がある場合は、入院時の保障が充実した商品を選ぶと安心です。
ただし、その分、保険料も高くなります。
(※)
参考:公益財団法人 生命保険文化センター:リスクに備えるための生活設計
ポイント③手術時の保障内容
手術が必要になった場合、民間の医療保険に加入していれば、契約時に設定した額の給付金を受け取れます。
給付される金額は、手術の種類ごとに決められている10倍・20倍・40倍などの倍率を入院給付金日額にかけて計算するもののほか、手術内容にかかわらず決まった金額が支払われるタイプがあります。
どの程度の金額に設定すればよいのか判断が難しいため、高額療養費制度も考慮しましょう。
高額療養費制度とは、自己負担限度額(多くの場合は10万円)を超える医療費を支払った際、申請することで限度額超えた分の払戻を受けられる仕組みのことです。
言い換えれば、高額療養費制度を適用したとしても10万円程度の自己負担額が発生する可能性があるといえます。
経済的な負担を抑えたい場合は、10万円程度の手術給付金が受け取れるよう設定するのがおすすめです。
ポイント④保険料の払込期間
保険料の払込期間は「短期払い」と「終身払い(全期払い)」の2種類です。
短期払いは、保険期間よりも短い期間で払い込みを終えられるため、終身払いに比べて総支払額が少なくなるのが特徴です。
払込期間満了後は保険料を負担することなく、保障を受けられる形です。
一方、終身払いは短期払いと比較すると毎月の保険料は割安である一方で、保険料の払い込みは一生涯にわたって行うことになります。
短期間で払い終えるか、毎月の負担を抑えて長期間支払うか、どちらが自分に適しているか検討しましょう。
ポイント⑤特約
特約とは、必要な場合に付け加えるオプションのことです。
基本的な入院・手術の保障内容に加え、自身が心配しているものや手厚く備えたいと考えている疾病リスクに備えられるための特約を検討します。
代表的な特約は、以下のようなものです。
【主な特約】
入院一時金 病気やケガで入院した際に入院日数にかかわらず、一律で一時金を受け取れる
特定疾病特約 がんや脳卒中といった特定の病気にかかった際に手厚い保障を受けられる
女性疾病特約 乳がんや子宮がんなどの女性特有の病気にかかった際に手厚い保障を受けられる
先進医療特約 通常の医療保険では保障対象外となる先進医療を受けた場合に給付金を受け取れる
通院特約 病気やケガで入院・退院後に通院が必要となった場合に給付金を受け取れる
用意されている特約は選択する保険会社や商品によって異なるので、自身が求めている特約を選択可能なものを選ばなければなりません。
ポイント⑥保険のタイプ
掛け捨て型と、貯金型があります。
このどちらを選択するかを検討するのも選び方の大きなポイントといえるでしょう。
掛け捨て型の場合、解約返戻金がほぼないか、あってもごくわずかです。
ただし、月々の保険料が貯蓄型と比較して安く設定されている特徴を持ちます。
一方、貯蓄型は掛け捨て型と比較して保険料が高めに設定されているものの、条件を満たした場合に還付給付金を受け取れるタイプです。
掛け捨て型は保険料が安いものの、損をするのではないかと考える方もいるでしょう。
ですが、貯蓄型と比較して商品数が多いため、自分にぴったりの保険を選びやすくなります。
貯蓄型は掛け捨てにならないのがメリットではありますが、商品数が少ないのがデメリットです。
また、貯蓄型といっても、支払った以上の保険料が戻ってくるものではないことについて理解しておきましょう。
契約してから短期間で解約した場合は元本割れになる点にも注意が必要です。
ポイント⑦日帰り入院の保障の有無
近年は入院をすることなく、日帰りへ対応できる病気やケガも増えてきました。
そのため、長期入院保障に関することだけではなく、日帰り入院の保障の有無についても考えておかなければなりません。
保険商品によっては日帰り入院では保証されないものもあります。
ただ、そういった場合は特約で入院一時金特約をつけるのも一つの方法です。
特約を含めると保険は複雑になりますが、比較しながら自分に合ったものを選びましょう。
自分に合った医療保険を選ぶときの流れ
保険の選び方を考えるうえで何より重要なのが、自分に合った保険を選ぶことです。
どれほど優れた商品でも、自分に合わなければ十分な保障にはなりません。
そこで、自分に合った医療保険を選ぶにはどうすればよいのか、全体的な流れを紹介します。
保険の加入目的を明確にする
まずは、どのような目的で医療保険に加入しようと考えているのか明確にしておきましょう。
「何となく将来が不安だから」「入っておいた方がよいと人に勧められた」という方もいるはずです。
ですが、保険は選択する商品によって特徴が異なり、その中から適した商品を選ばなければなりません。
目的を明確にしておかないと保険選びは難しくなります。
どのような場面で手厚く備えておきたいのか考えておきましょう。
たとえば「ケガや病気で、先進医療が必要になったときの不安を抑えたい」「遺伝的にがんのリスクが高いため、がんにしっかり備えたい」などの目的です。
目的が明確であれば、選ぶべき保険や特約を判断しやすくなります。
保障内容を考える
保険商品によって大きく異なるのが、保障内容です。
特に、以下の4つはしっかりと考えておきましょう。
【保障内容の注目ポイント】
- 入院給付金日額
- 手術給付金額
- 1入院あたりの支払限度日数
- 日帰り入院に対する保障
病気やケガで入院した場合、一日あたり受け取れる給付金が入院給付金日額です。
軽く触れたように、公益財団法人 生命保険文化センターの調査によると、入院時の一日あたりの自己負担費用の分布で特に多いのは10,000円~15,000円となっています。(※1)
また、生命保険加入者の入院給付金日額設定に関する調査をみてみると、男性は9,600円、女性が8,100円でした。
金額の分布でいうと、男性は10,000~15,000円未満、女性は5,000~7,000円未満を設定している人が最も多い結果です。(※2)
このあたりも参考にしながら、いくらの入院給付金日額にするか検討してみるとよいでしょう。
手術給付金については、手術の種類ごとに決められた倍率を入院給付金日額にかけるか、手術内容ごとに決まった金額が支払われます。
倍率が固定されているタイプは、手術を受けた場合に一律の給付金が受け取れるのはメリットです。
ただ、体への負担やリスクに応じて手厚い給付金で備えたいと考えている方は、倍率が変動するタイプの方が向いていることもあります。
注意しなければならないのが、1入院あたりの支払限度日数です。
1回の入院に対し受け取れる入院給付金は上限が定められています。
支払限度日数を長くするほど保険料は高くなってしまいますが、どの程度保険料を支払えるのかも含めて検討しましょう。
日帰り入院に関する保障も欲しいと考えているのであれば、どのような保障が用意されているかもチェックしてみてください。
(※1)
参考:公益財団法人 生命保険文化センター:リスクに備えるための生活設計
(※2)
参考:(PDF)公益財団法人 生命保険文化センター:2022(令和4)年度生活保障に関する調査[PDF]
特約を付加するか考える
少し難しいと感じやすいのが、特約に関することです。
保険商品にはさまざまな特約がありますが、必要以上に追加すると保険料が高額になります。
特約の内容についてよく理解することも重要です。
理解せずに契約すると、自分にとって不要な特約を選んでしまう可能性があります。
現時点で必要ないものは加入後に改めて検討してみるのもよいでしょう。
ただし、中には加入と同時にしか特約をつけられないものもあるので注意してください。
また、特約は自分が手厚く備えたい部分に安心をプラスできるものではありますが、特約を付けるよりも、特化した保険に加入したほうが手厚い保障を受けられる場合もあります。
全体的に比較検討することが大切です。
保険期間や保険料の払込期間を考える
どの程度の期間備えたいのか、保険期間を考えておきましょう。
保険料の払込期間については、紹介したように保険期間中は支払いが続くものと、保険期間よりも短く払い込みが完了するものもあるため、自身に合った方を選んでいきます。
保険のタイプを考える
保険のタイプとして主に考えなければならないのが、掛け捨て型と貯蓄型のどちらにするかです。
どちらが優れているとは一概にいえません。
それぞれの特徴をよく理解したうえで選んでみてください。
民間の医療保険の選び方
民間の医療保険を選ぶ際、すべての商品を比較するのは大変なことです。
そこで、年代・性別・加入目的からみた選び方を押さえておきましょう。
年代で選ぶ
年代によって必要な保障は変わってきます。
20代のうちはまだ大きな病気のリスクが低いため、最低限の保障にするのも一つの方法です。
ただ、若いうちに保険料が安い終身医療保険に加入しておくと、保険料を抑えて払い続けられます。
30代以降は少しずつ病気のリスクが高くなるほか、結婚・出産などでライフスタイルも変化しやすいので、保障を充実させることも検討するとよいでしょう。
性別で選ぶ
男性と女性ではかかる病気の種類やリスクが異なります。
たとえば、男性に多くみられる疾患は、糖尿病や狭心症、心筋梗塞、脳卒中などです。
女性の場合は、女性特有の病気である乳がんや子宮がん、子宮筋腫などのリスクを考えておかなければなりません。
これらの保障を手厚く備えておきましょう。
加入目的で選ぶ
特定のリスクに備えたいと考えて医療保険の加入を検討している場合は、その目的に合った商品を選びましょう。
たとえば「がんに手厚く備えたい」「女性特有の病気にかかったとき、治療費の心配を抑えたい」など、目的を明確にしたうえで選ぶことが重要です。
定期的な医療保険の見直しも大切
一度加入した医療保険は何も考えることなくそのまま加入を続けるのではなく、定期的に見直しをすることが重要です。
たとえば、20代で加入した場合、30代、40代となると、20代とはかかりやすい病気のリスクも変わってきます。
特に、若いうちに加入した医療保険には死亡保障をつけていない方もいるのではないでしょうか。
年齢を重ねていくにつれ、死亡保障を手厚くする方も多いようです。
現在どのような内容の医療保険に加入しているのかよく確認したうえで、不足している保障などがあれば、見直しや乗り換えも検討してみてください。
持病や既往歴があっても医療保険は入れる?
医療保険というと、健康な方でなければ加入できないイメージを持っている方もいるはずです。
ですが、以下のような保険であれば加入可能です。
ただし、通常の商品よりも保険料は割高になります。
まずは通常の商品への加入を検討し、難しい場合に選択肢とするのがよいでしょう。
引受基準緩和型医療保険
一般的な保険商品と比較して加入の条件が緩められているものや、告知しなければならない項目が限定的なものを引受基準緩和型医療保険と呼びます。
限定告知型医療保険とも呼ばれるもので、持病や既往歴がある方でも加入しやすいのが特徴です。
無選択型医療保険
告知なしで誰でも加入可能なのが無選択型医療保険です。
持病や既往症がある方でも断られることはありませんが、保険料は引受基準緩和型医療保険より高めに設定されています。
他にも免責事由が多い、保険期間が限られているなどのデメリットもあるので、よく確認しておきましょう。
また、無選択型医療保険の多くは、加入時に治療中の病気が保障対象外となるケースが多くあります。
現在治療中の病気が悪化したときに備えたいと医療保険を検討している方は、目的に沿った保険とはいえないことがあるので注意してください。
選び方のポイントをよく押さえたうえで検討することが大切
いかがだったでしょうか。
医療保険の選び方や注意点を紹介しました。
自分に合った保険選びをする際の流れなどもご理解いただけたかと思います。
保険は商品が多いので悩んでしまいますが、自分に合ったものを見つけましょう。
どの保険がよいかわからない場合は、ぜひほけんスマイルにご相談ください。
プロのアドバイザーがご希望をお聞きしながらおすすめの保険を紹介しています。
万が一の病気やケガにしっかり備えていきましょう。
お客様の声

親身になって必要な
保険を教えてくれました!
30代男性保険見直し生命保険
30代に入り家族も増え、真剣に将来のことを考え始めたところでした。そんな時、友人に勧められ訪れました。私のライフステージに合わせた生命保険の提案をしてもらえました。特に子供の教育資金や将来のリスク管理に関するアドバイスが具体的で、非常に参考になりました。ほけんスマイルの方々は知識が豊富で、安心して相談に乗ってもらえる環境が整っていました。今後も家族の安全を守るために、ほけんスマイルと長く関わっていくつもりです。

新規で生命保険に加入して、
未来への安心を手に入れました!
20代女性新規加入生命保険
保険のことは難しくてよくわからなかったのですが、ほけんスマイルのスタッフさんがとても親身になってくれて、自分にとって最適な保険プランを提案してくれました。
私でも理解しやすいように、細かいポイントまで説明してくれたので、安心して加入することができました。これで万が一の時も安心です。

医療保険への新規加入で
安心を得ました!
30代女性保険見直し医療保険
医療保険を見直したいと思いつつ、どの代理店に相談すれば良いのか分からなかったのですが、知人に勧められたほけんスマイルで相談して大正解でした。
30代という節目での見直しに対して、具体的で実用的なアドバイスを受けることができ、保険内容も大幅に改善されました。