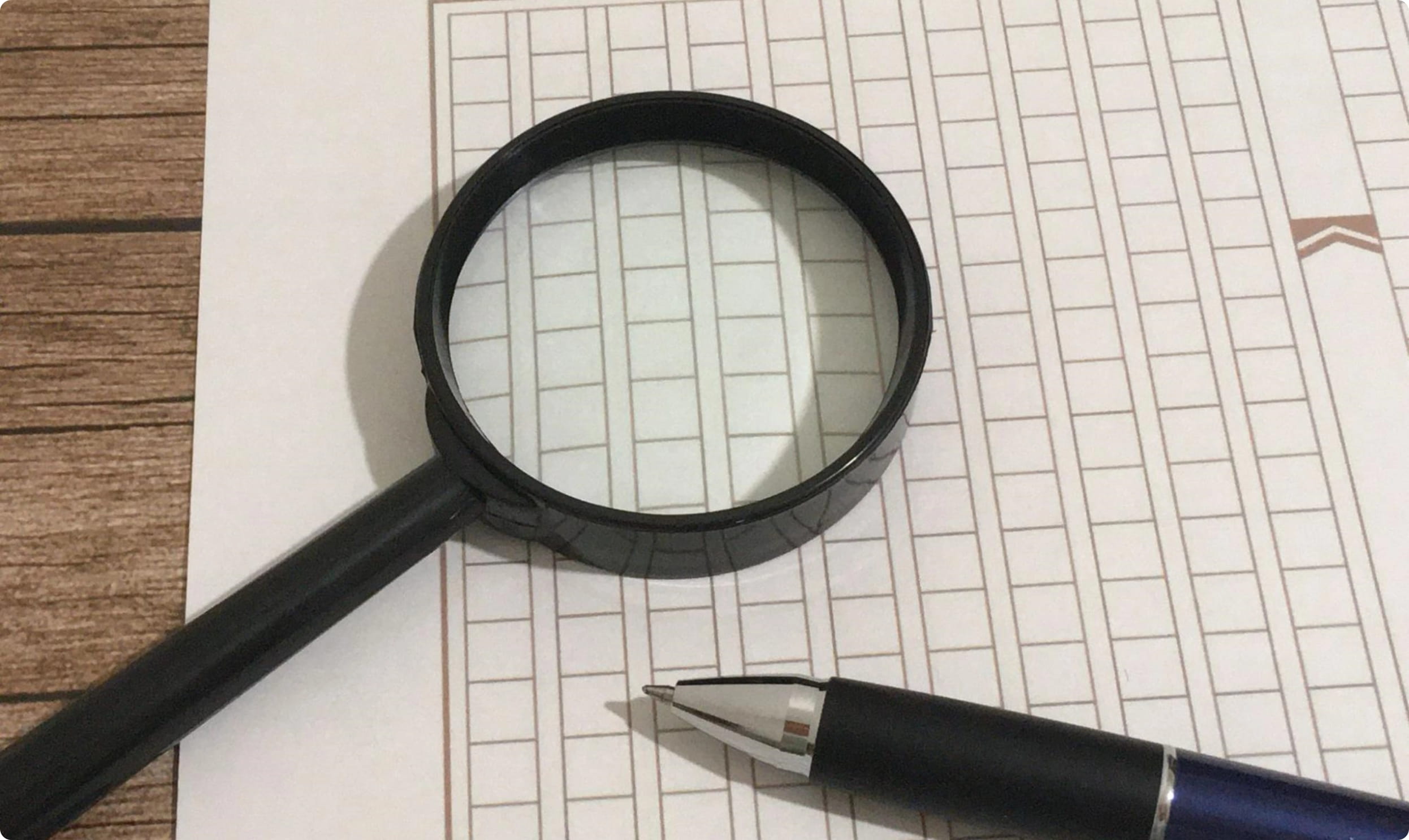学資保険に入ってない家庭の割合とは?他に検討したい選択肢も紹介
2025.04.30

学資保険は、子どもの将来に備えるための保険です。子どもの教育費が年々増加する現代において、学資保険は親にとって大きな安心材料となります。
控除を受けられ、計画的に教育資金を確保できる点がメリットです。しかし、デメリットもあるため、他の選択肢と比較することが重要です。どのような場合に学資保険が役立つのか、保険商品としての特徴を押さえておくことが大切です。
この記事では、学資保険にかかる平均的な費用や入らない人の理由、メリット・デメリットについて紹介しています。加入の最適なタイミングや確認すべきポイントも、ぜひ参考にしてください。
目次
学資保険に入っていない人の割合は?
生命保険などを取り扱うソニー生命が2024年1月31日〜2月1日に実施した調査「子どもの教育資金に関する調査2024」によれば、子どもを大学等へ進学させるための教育資金として、銀行預金(56.4%)の次に多いのが、学資保険(43.7%)の積み立てでした。(※)
一方、教育資金に学資保険を含んでいない人の割合は全体の56.3%です。全体の約6割は、銀行預金など学資保険以外の方法で教育資金を確保していることがわかります。
※本調査は複数回答形式のため、学資保険と銀行預金、学資保険と教育ローンといった複数の準備方法を併用している人も含まれています。
※参照元:ソニー生命「子どもの教育資金に関する調査2024」
https://www.sonylife.co.jp/company/news/2023/nr_240312.html
学資保険にかかる平均費用
「オリコン顧客満足度ランキング」のアンケート調査によれば、調査対象者が1ヶ月あたりに支払っている保険料の割合は次のようになりました。(※)
| 1ヶ月あたりの保険料 | 割合 |
| 3,000円未満 | 1.9% |
| 3,000〜5,000円未満 | 4.2% |
| 5,000~7,500円未満 | 5.8% |
| 7,500~10,000円未満 | 13.4% |
| 10,000~15,000円未満 | 35.2% |
| 15,000~20,000円未満 | 15.9% |
| 20,000~25,000円未満 | 8.4% |
| 25,000~30,000円未満 | 4.5% |
| 30,000~40,000円未満 | 4.3% |
| 40,000~50,000円未満 | 2.8% |
| 50,000円以上 | 3.7% |
月払い・半年払い・年払いの利用者を含めた1,877人のアンケート結果では、1ヶ月あたりの保険料として最も多かったのは10,000円~15,000円の範囲でした。全体では7,500円~20,000円未満がボリュームゾーンとなっています。
保険料は契約内容によって異なりますが、おおよその相場は10,000円前後~20,000円と考えられます。
※参照元:オリコン顧客満足度ランキング「学資保険は月々いくら?保険料の平均相場や満額受け取り時の金額目安を解説」
https://life.oricon.co.jp/rank-educational-insurance/special/knowledge/cost/
学資保険に入らない人がいる理由
銀行預金や教育ローンのように、学資保険に入らず教育資金を準備するケースもあります。
学資保険に入らない理由は次のとおりです。
返戻率が低い
学資保険の返戻率は、保険料の支払総額に対して実際に受け取れる金額の割合です。返戻率は%で表され、100%を超えると、支払総額よりも多い金額が受け取れることを意味します。
学資保険に入らない理由として、返戻率が低く見返りが少ないため、支払いを続けるメリットがないと判断するケースがあります。そのため、株式投資のようなハイリターンの方法を検討するケースもあります。
学資保険などの保険商品は、多くが固定金利となっています。加入後に政策金利が引き上げになると、学資保険の金利は変動しないため、返戻率が下がってしまう可能性があります。
元本割れのリスクがある
学資保険は必要なタイミングで引き出せない商品が多く、さらに中途解約で返戻金が支払総額を大きく下回る元本割れのリスクがあります。
銀行預金は途中で引き出しても元本が減るだけですが、学資保険は中途解約するとほとんどの場合、元本割れになります。
教育資金が緊急で必要になった場合に、やむを得ず学資保険を解約しなければならないことを考えると、支払総額の100%を受け取れないリスクは懸念材料になるでしょう。
また、返戻率が100%を下回った場合、解約の有無にかかわらず手元に戻るお金は支払総額よりも少なくなります。2016年以降は政策金利がマイナスに転じているために、学資保険の返戻率は低水準のまま推移している状況です。
インフレに弱い
インフレーションとは、モノ・サービスの値段が上昇することです。インフレが発生すると金利が上昇しますが、学資保険の金利は固定のため、金利上昇の恩恵を受けることはできません。
家庭では、インフレによって物価が上昇し家計への負担が大きくなります。保険料の支払いが負担となる可能性があり、支払いが滞ったり中途解約が発生したりするリスクを考慮する必要があります。
学資保険は契約期間が数年~10年以上と長期にわたるため、インフレリスクが高い商品です。インフレ時のデメリットを十分に考慮して契約する必要があります。
流動性・柔軟性には欠ける
学資保険は満期を迎えるまで基本的に引き出せないため、流動性や柔軟性に乏しく、急な支出に対応しにくいという問題があります。
たとえば、預金のように必要な金額をリアルタイムに引き出して使うことはできません。しかし教育資金は子どもの成長とともに発生するものです。塾や習い事、留学といったさまざまな教育ニーズに対応するためには、学資保険の満期を待たずに必要な額を手元に残しておく必要があります。
中途解約で元本割れを起こすリスクも含めると、契約前に流動性・柔軟性に欠けるデメリットを考慮しなければならず、結果として加入を見送る方が少なくないようです。
十分な貯金がある
すでに十分な蓄えがある場合は、無理に学資保険へ加入する必要はありません。返戻率が非常に高い学資保険であればメリットはありますが、返戻率が低い商品は通常の預金と比較してあまりメリットが感じられない可能性があります。
蓄えをそのまま教育資金に回せば、契約や支払いの手間がかからず必要な費用を捻出できます。教育資金が必要になったタイミングで自由に使えるため、契約した保険商品やローンを解約する手間がかかりません。
学資保険に入るメリット
学資保険にはデメリットだけでなく、多くのメリットもあります。預貯金や投資と比較し、メリットも確認しておきましょう。
「計画的に教育資金を貯められる」「契約者に万が一のトラブルがあっても備えられる」「生命保険控除が受けられる」という3つのポイントをチェックしていきましょう。
計画的に教育資金を貯められる
学資保険は毎月一定の金額を払い込むシステムのため、計画的に教育資金を貯蓄できます。満期まで自由に引き出せないため、半強制的に積み立てられ、使い込んでしまう心配もありません。
自力で貯蓄しようとすると、どうしても他の支出とのバランスをとらなければならず、優先度の高いものにお金を使ってしまう場合があります。その結果、教育資金の貯蓄に時間がかかったり、目標金額に到達できなかったりする可能性があります。
その点、学資保険は自動でお金が引き落とされるため、「他のことにお金を使ってしまい余裕がなくなる」といったトラブルを防ぐことができます。「貯金しなければ」とやりくりに悩む心配もなく、計画どおりに必要な金額を貯められます。
契約者に万が一のことがあっても備えられる
学資保険の契約者が死亡・高度障害状態になった際には、保険料の支払いが免除されます。さらに、契約時に取り決めた満期保険金を家族が受け取れるため、教育資金を失う心配がありません。
契約者の多くは被保険者の両親や祖父母です。そのため、病気やその他の理由で万が一の事態が発生しても、学資保険の保障によって予定どおりに教育資金を受け取ることができます。
また、子ども自身の死亡保障や養育年金を付帯した商品を選べば、さらに手厚い教育費のサポートとして機能します。子どもの将来を考えた場合、契約者と被保険者の立場に応じた保障内容を選ぶことが重要です。
生命保険料控除が受けられる
学資保険は、生命保険料控除の対象となり、一般生命保険料控除が適用されます。生命保険料控除とは、支払った生命保険料に応じて一定の金額が契約者の所得から差し引かれる制度です。
学資保険は、子どもなどの教育資金を積み立てる貯蓄としての役割と、契約者が死亡または高度障害状態に陥った際に保険料の払い込みを免除する生命保険の保障を併せた保険商品です。そのため、所得控除の一種である生命保険料控除を利用することができます。
2012年1月1日以降に締結された学資保険契約は、新制度と呼ばれます。旧制度とは区別され、次の計算式で控除額を求めます。
| 年間の支払保険料 | 控除額 |
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000〜40,000円 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000〜80,000円 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円〜 | 40,000円(一律) |
所得が少ない場合、控除のメリットは小さくなりますが、一定の給与がある場合は、所得控除によって所得税や住民税が軽減され、家計の負担を抑えられます。
学資保険は入らなくても良いのか?
学資保険の必要性は、各家庭の状況によって異なります。すでに十分な貯蓄があれば、そこから資金を確保できるため、学資保険への加入は不要かもしれません。
しかし、近年では教育の選択肢が多様化し、大学卒業後に大学院やその他の教育機関へ進学するケースも増えています。そのため、十分な教育費を準備したいと考える家庭が多いのではないでしょうか。
子どもの教育には、塾・習い事・留学費用・受験費用・教材費などさまざまなお金がかかります。貯蓄だけで賄える場合は、学資保険に加入しない選択肢もあります。しかし、半強制的かつ自動で積み立てられる学資保険なら、まとまった金額を貯蓄することができます。
例として、公立・私立の幼稚園から大学までの教育費(1年あたり)は次のとおりです。
| 教育費/年 | 公立 | 私立 |
| 幼稚園 | 16万5,126円 | 30万8,909円 |
| 小学校 | 35万2,566円 | 166万6,949円 |
| 中学校 | 53万8,799円 | 143万6,353円 |
| 高校 | 51万2,971円 | 105万4,444円 |
| 大学 | 92万7,668円 | 117万6,894円 |
公立は私立よりも割安な印象がありますが、子どもの進路によっては、公立から私立へ転校したり、公立高校から私立大学へ進学したりすることも考えられます。そのため、上記の例よりもさらに費用がかかる場合があります。
計画的に貯蓄できる学資保険は、被保険者である子どもの将来を支える心強い手段です。各家庭の方針にもよりますが、教育資金は計画的に貯めておく必要があり、そのために学資保険が役立ちます。
参考記事:文部科学省「結果の概要-令和3年度子供の学習費調査(国公私立大学の授業料等の推移)」
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa03/gakushuuhi/kekka/k_detail/mext_00001.html
学資保険に加入する際のベストタイミング
学資保険は中長期にわたって保険料を支払い、教育資金を確保するものです。加入時期が早いほど長く支払いを続けることができるため、お子さんが生まれたら、できるだけ早く加入を検討するとよいでしょう。
0~2歳までに加入するケースが一般的ですが、強制ではありません。家計の状況に応じて、3歳以降も加入を検討できます。学資保険は6,7歳くらいまで加入できるものが多いため、積み立ての期間を考えて早めに契約することをおすすめします。
学資保険に加入する際に確認すべきポイント
学資保険に加入する際に確認すべきポイントは、「返戻率」「保障内容」「受け取り時期」の3つです。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
返戻率
返戻率とは、学資保険の支払総額に対して受け取れる金額の割合です。「受取率」「戻り率」「払戻率」とも呼ばれています。
実際に受け取れる金額がいくらになるのかを考えるうえで、この返戻率が重要になります。計算式は次のとおりです。
返戻率(%)=受取総額/払込保険料総額✕100
この計算式に当てはめて、100%以上であれば満期保険金や祝い金などとして、払い込んだお金と同額のお金を受け取れます。
保障内容
学資保険は、満期を迎えたときに「満期保険金」や「祝い金」の名目でお金が受け取れます。さらに医療保障や育英年金が付帯しているものもあり、保障内容を比較して将来にふさわしい商品を選びましょう。
特約には、医療保障と死亡保障があります。医療保障は入院給付金や手術給付金が受け取れるものです。一方、死亡保障は契約者に万が一の事態が発生した際に、学費を受け取れるよう保障するものであり、育英年金や保険料払込免除特則が含まれます。
特約を付加して万が一に備えると安心ですが、返戻率が低くなる点には注意が必要です。
受け取り時期
払込保険料は、返戻率に応じた金額を満期時に受け取ることができます。途中で解約すると返戻率が下がるため、払い損にならないよう注意が必要です。
学資保険は子どもの進学に備えるためのものであり、主に高校や大学、または大学修了後の留学や大学院進学の準備資金として利用されます。
このうち、もっとも教育費用がかかる段階が大学進学のタイミングといわれていますが、進路によってはその前後になる可能性もあるため、受け取り時期は慎重に設定しなければなりません。
学資保険の代わりになる教育資金の準備方法
学資保険の代わりに教育資金を準備する方法としては、貯蓄・ローンのほかに保険や投資信託(投信)などがあります。
たとえば、貯蓄は毎月の給料から一定の金額を教育資金に回す方法のほかに、児童手当のような制度を活用して、国からもらうお金をやりくりしながら教育資金を貯める方法もあります。
学資保険以外の保険商品には、「低解約返戻金型終身保険」「外貨建て終身保険」「個人年金保険」といった種類がありますが、どのような特徴があるのでしょうか。
投資信託も含め、各保険の特徴を詳しく解説します。
低解約返戻金型終身保険
低解約返戻金型終身保険は、死亡や高度障害などの保障が一生涯続いている終身保険です。
保険料払込期間中の解約返戻金は、払込年月や経過年月数に応じて計算され、70%程度に抑えられています。そのため、中途解約すると返戻率が低くなりますが、払込期間が満了すると返戻率は上昇します。
払込期間は3種類に分けられます。
| 名称 | 払込期間の決まり方 |
| 歳満了 | 被保険者の年齢を60歳や65歳のように決めて、その年齢まで払込期間が発生するもの |
| 年満了 | 「10年」「20年」と年数で払込期間が決まるもの |
| 終身払い | 払込期間を特に定めずに被保険者が死亡するまで保険料を払い込む方法(終身払い)から選べるもの |
他の保険商品と同様に、ニーズに合わせて保障を選び、特約を付加して自分に合った保険商品を設計できます。
外貨建て終身保険
外貨建て終身保険は、保険料を外貨で支払い、外貨で受け取るシステムの終身保険です。
外貨で運用し、利益を得られる保険商品として知られています。保険期間は一生涯で、日本円よりも金利の高い通貨を選ぶと利回りが高くなります。
ただし、為替レートの変動や手数料が発生するため、注意が必要です。また、元本割れのリスクもあるため、十分に理解しておきましょう。
この保険商品は費用や仕組みをよく把握し、損失のリスクを理解する必要があります。ドル建てなどで運用し、利益を返戻金に上乗せして受け取ることができます。
個人年金保険
個人年金保険とは、老後資金を蓄えるための年金保険です。契約時に年齢を決めて、その年齢まで払い込むと年金が受け取れる仕組みです。
個人年金保険・学資保険はどちらも生命保険の一種なので、貯蓄のために契約利用できます。たとえば、子どもの教育資金が必要になるタイミングに満期を設定すれば、その年まで払い込みを続けて必要な資金を積み立てられます。
個人年金保険は、健康状態の告知や医師の診査が不要なものを選べます。健康状態に不安がある方、既往症や既往歴のある方で、学資保険に申し込みづらい場合は個人年金保険を選択肢に加えられます。
ただし、個人年金保険には、払い込んだ保険料以上の死亡保障は付帯していません。保険料の払込免除も受けられないため、学資保険と比較して保障内容が十分かどうかをよく考慮しましょう。
投資信託
投資信託は、投資家から集めた資金を株式・債券・不動産などで運用し、利益を分配する金融商品です。
返戻率が低い学資保険の代わりに、投資で高いリターンを期待できる金融商品です。元本割れのリスクはありますが、分散投資や長期的な投資の継続によってリスクを軽減できます。
一例として、契約から15年間、毎月32,000円(元本576万円)を投資し、年利7%で運用できた場合、収益は約438万円となります。累計すると1,000万円程度になります。ただし、運用成績は保証されるものではありません。
株式や不動産投資のように、自分で投資を行う方法も選べます。しかし、仕組みを理解していなければ、思わぬ損失につながる可能性があります。プロに運用を任せられる投資信託は、投資が初めての方でも取り組みやすい積み立て方法といえるでしょう。
学資保険に入ってない場合でも慎重に貯蓄方法を選ぼう
今回は、学資保険に入ってない家庭の割合、教育にかかる平均的な費用や学資保険のメリット・デメリットを紹介しました。
学資保険は子どもの学費を準備する方法の一つですが、教育資金の貯め方には、投資やその他の保険商品など、さまざまな選択肢があります。投資信託や新NISAなどの方法も、現代では一般的になっています。
しかし、投資は必ず利益が出るとは限らず、損失のリスクも考慮する必要があります。
学資保険は投資のようなハイリスク・ハイリターンではありませんが、着実にお金を積み立てられる仕組みになっています。ぜひ本記事を参考に、学資保険への加入を検討してください。
お客様の声

親身になって必要な
保険を教えてくれました!
30代男性保険見直し生命保険
30代に入り家族も増え、真剣に将来のことを考え始めたところでした。そんな時、友人に勧められ訪れました。私のライフステージに合わせた生命保険の提案をしてもらえました。特に子供の教育資金や将来のリスク管理に関するアドバイスが具体的で、非常に参考になりました。ほけんスマイルの方々は知識が豊富で、安心して相談に乗ってもらえる環境が整っていました。今後も家族の安全を守るために、ほけんスマイルと長く関わっていくつもりです。

新規で生命保険に加入して、
未来への安心を手に入れました!
20代女性新規加入生命保険
保険のことは難しくてよくわからなかったのですが、ほけんスマイルのスタッフさんがとても親身になってくれて、自分にとって最適な保険プランを提案してくれました。
私でも理解しやすいように、細かいポイントまで説明してくれたので、安心して加入することができました。これで万が一の時も安心です。

医療保険への新規加入で
安心を得ました!
30代女性保険見直し医療保険
医療保険を見直したいと思いつつ、どの代理店に相談すれば良いのか分からなかったのですが、知人に勧められたほけんスマイルで相談して大正解でした。
30代という節目での見直しに対して、具体的で実用的なアドバイスを受けることができ、保険内容も大幅に改善されました。