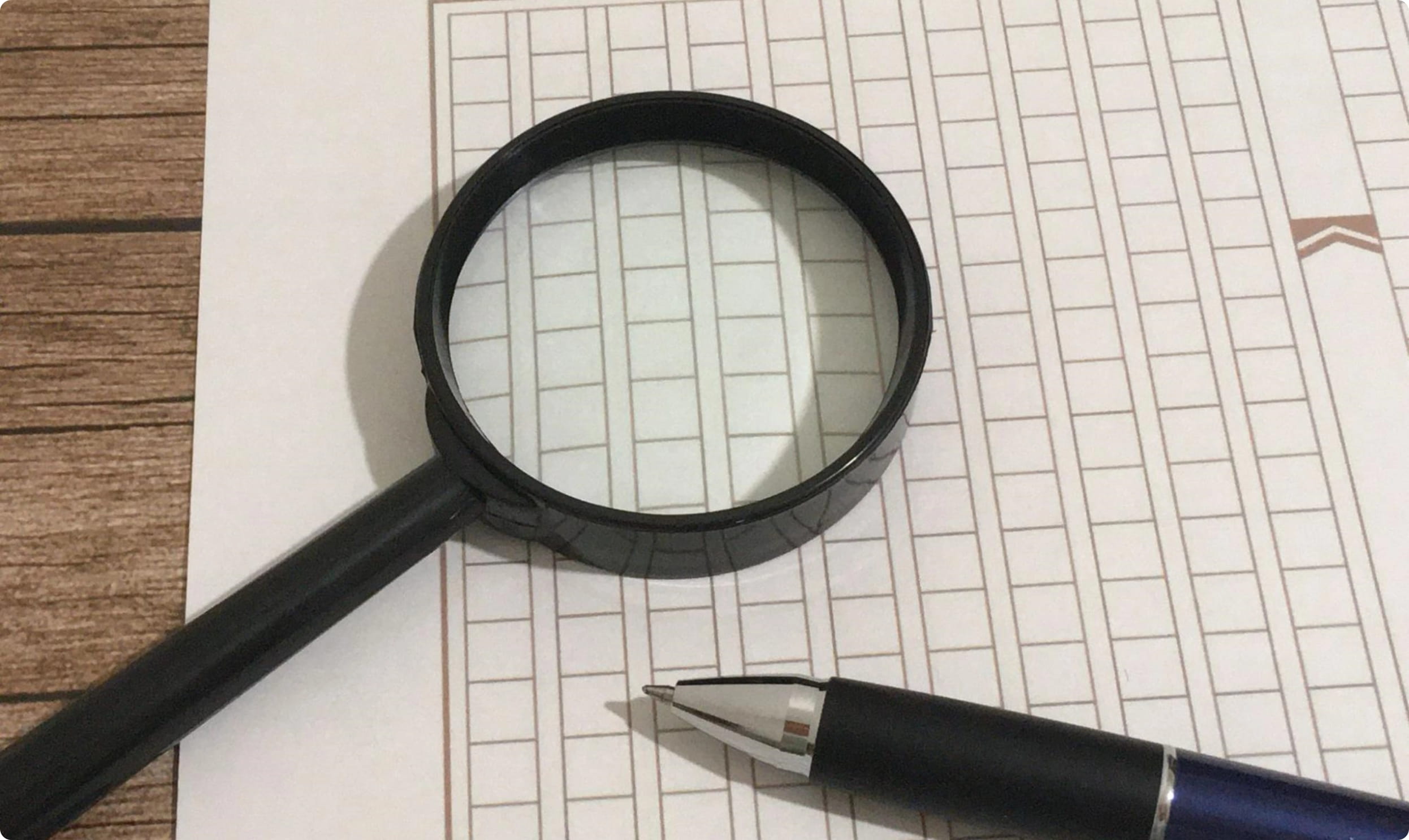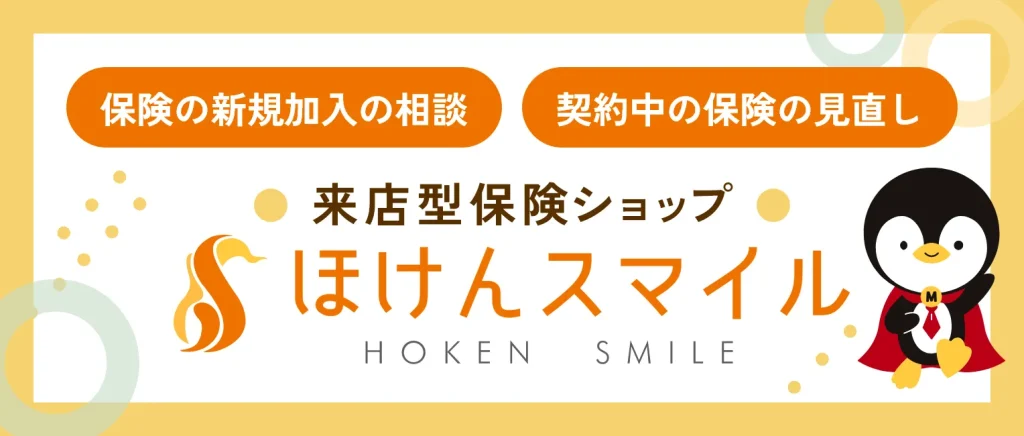生命保険で積立?貯蓄型のメリット・デメリットで向いている方が分かる
2022.08.16

「将来へ向けて生命保険を考えているけど、どんな保険があるのか分からない」「掛け捨て型保険と貯蓄型保険ってどっちがいいの?」と悩んでいませんか。
生命保険には、掛け捨て型の保険と貯蓄型の生命保険の2種類があり、今回は生命保険について詳しく知りたい方に向けて貯蓄型の生命保険の概要を説明しています。
代表的な保険の種類や特徴、メリット・デメリットはどんなものなのでしょうか。
生命保険に悩んでいる方へ貯蓄型保険を分かりやすく解説していますので、お最後までお読みください。
目次
貯蓄型の生命保険とは
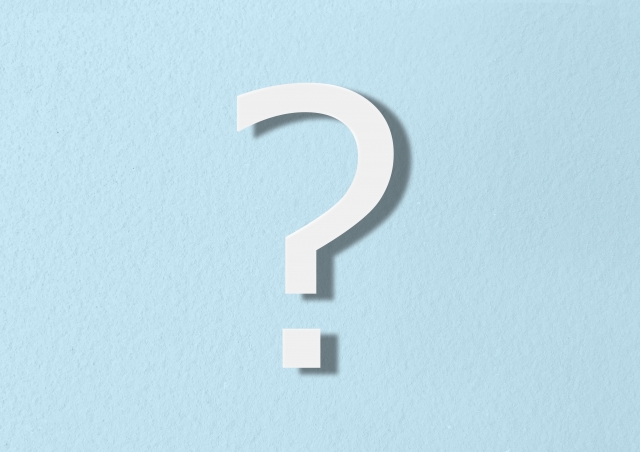
貯蓄型の生命保険とは、病気や怪我などに対する「保障」と、将来への備えとしての「貯蓄」という2つの要素を持ち合わせた保険を指します。
月々の保険料の支払いにより、保障と貯蓄を同時にカバーできる、一石二鳥の保険商品です。
長期契約であるため、簡単には預金を引き出せませんが、言い換えれば確実な貯蓄を行えるというメリットがあります。
契約が満期をむかえれば満期保険金を受け取れ、また、契約の途中で解約したときでも、解約返戻金を受け取れます。
貯蓄型生命保険の種類と特徴

ここでは貯蓄型の生命保険の5つの種類と、特徴をお伝えします。
➀終身保険
終身保険(死亡保険)は被保険者が死亡、または高度障害状態になったときに保険金を受け取れる保険です。
契約期間は一生涯にわたるため、「満期」という概念はなく、したがって満期保険金は設定されていません。
その代わり、途中解約により、解約返戻金が被保険者に支払われます。
関連記事:保険の終身・定期とは?それぞれの概要とメリット・デメリット
②養老保険
被保険者が満期までに亡くなった場合は保険金を、満期をむかえた場合は満期保険金を受け取れるのが養老保険です。
なお、上述したどちらのケースにおいても、支払われる金額は同じです。
満期保険金の有無と、保険期間が設定されている点において、終身保険と異なります。
保険期間は、期間または年齢により任意で設定できます。
そのため、子どもの成長や退職といった人生のイベントを見据えて、計画的に保険期間を設定可能です。
③学資保険
学資保険は、教育資金の貯蓄にフォーカスした保険です。
毎月決まった額の保険料を支払い、満期をむかえたら進学準備金や留学金として満期保険金を受け取れます。
加入のタイミングが早ければ早いほど月々の保険料を抑えられるため、家計の負担を軽減しつつ子どもの将来に備えられます。
なお、万が一被保険者が亡くなった場合、あるいは高度障害状態に陥った場合は、満期までの支払が免除になるうえ、満期をむかえると満期保険金の受け取りが可能です。
【関連記事】
学資保険の選び方!わが子のために押さえておきたいポイント
学資保険の返戻率とは?返戻率を高くする4つの方法を解説
学資保険の受取人は誰にすべき?契約時のポイントを解説!
④個人年金保険
国民年金や厚生年金などの公的年金だけでは不安を感じる方にとって、個人年金保険は老後の資金確保の選択肢の一つです。
さらに、個人年金保険は「個人年金保険料控除」または「一般生命保険料控除」といった所得控除が受けられるのもメリットです。
なお、個人年金保険は大きく3つの種類に分けられます。
個人年金保険
| 概要 | 相続人の年金の受け取り可否 | |
| 終身年金 | 被保険者は亡くなるまでの一生涯年金を受け取り可能 | 年金の受取期間中に被保険者が死亡した場合、相続人は残りの年金を受け取れない※保証期間を付けた場合を除く |
| 確定年金 | 年金の受け取り期間を5年・10年・20年など、任意で設定できる | 年金の受取期間中に被保険者が死亡した場合、相続人は一時金、または年金を受け取れる |
| 有期年金 | 年金の受け取り期間が定められている | 年金の受取期間中に被保険者が死亡した場合、相続人は残りの年金を受け取れない※保証期間を付けた場合を除く |
なお、いずれの種類の場合においても、途中解約すると、基本的に解約返戻金が支払総額を下回ります。
⑤外貨建て保険
外貨建て保険とは、貯蓄型の生命保険のうち、保険料の一部をドルやポンドなどの海外の通貨で運用する仕組みのものです。
先述した終身保険や養老保険、個人年金などにも、それぞれ外貨建てプランが存在します。
資産の一部を外貨として運用することでリスク分散をはかれ、円の価値が下がるインフレへの備えともなります。
ただし、レートによって受け取れる保険料は上下し、予測が立てづらいというのは難点です。
関連記事:ドル建ての生命保険とは?メリット・デメリットも紹介
貯蓄型の生命保険のメリット

ここまで貯蓄型の生命保険の概要や種類を解説しました。
続いて、貯蓄型の生命保険の5つのメリットを紹介します。
メリット①解約返戻金や満期保険金を受け取れる
貯蓄型の生命保険の大きなメリットの1つとして、解約返戻金や満期保険金を受け取れる点が挙げられます。
毎月の保険料が貯蓄されていく点は、掛け捨て型の生命保険との大きな違いでもあります。
関連記事:生命保険の解約返戻金とは?受け取る際の注意点も解説
メリット②ライフイベントに合わせて費用を準備できる
子どもの進学や結婚、そして自身の退職など、人生におけるビッグイベントを見越して、資金を準備しておければ安心ですよね。
貯蓄型の生命保険なら、このようにまとまった資金が必要になるタイミングから逆算し、支払期間を調整することで、費用を準備できるというメリットもあります。
メリット③貯蓄と保障を兼ね備えている
月々の保険料の支払いだけで、いざという時への備えをしつつ、堅実に貯蓄できる点も大きな魅力です。
掛け捨て型とは違い、毎月の保険料が無駄になることは基本的にありません。
将来を考えるうえでは、万が一のときの保障はもちろん、貯蓄を増やす努力も重要です。
「とはいうものの、コツコツと貯蓄するのが苦手」という方は、貯蓄型の生命保険に加入することで、自動的に毎月貯金できるのです。
メリット④保険料以上の収益が発生する場合がある
契約内容や期間によって、支払った保険料以上の支払いを受けられる場合があります。
貯蓄型の生命保険に加入することは、個人の資産形成・運用の観点からも有効なのです。
メリット⑤契約者貸付制度を利用できる
貯蓄型の生命保険に加入していれば、契約者貸付制度を利用できるという利点もあります。
契約者貸付制度は、貯蓄型の生命保険に加入している方のみを対象として、解約返戻金の範囲内で借り入れを行える制度です。
この制度は、借入時の審査が不要であることに加え、カードローンよりも金利が低いといった特長を持ちます。
貯蓄型の生命保険のデメリット

貯蓄型の生命保険のメリットを押さえたうえで、ここからは、4つのデメリットを解説します。
デメリット➀資産運用の効率が悪い
貯蓄型の生命保険は、保険料を保険金の積み立てだけではなく、貯蓄にも回さなければならず、資産運用の効率がよいとはいえません。
貯蓄が行える分、資産運用の効率は悪いという一長一短の側面を持っています。
デメリット②保険料が高額である
貯蓄型の生命保険は、掛け捨て型の生命保険に比べて毎月の保険料が割高になる傾向にあります。
毎月の保険料で貯蓄の積み立ても行うため、どうしても月々の支払額が増えてしまうのです。
毎月の支払額が家計に与える影響を試算しつつ、慎重に勘案したいところです。
関連記事:生命保険に毎月いくら払ってる?世代や家族構成、年収別の平均を解説
デメリット③早期解約すると元本割れする場合がある
加入後、早期に解約すると解約返戻金が少ない、あるいは、解約返戻金そのものがないケースもあります。
これは、先述した貯蓄型の生命保険の運用効率の悪さに起因します。
短期の運用ではなかなか効果が出づらく、運用手数料が原資を上回ってしまうのです。
デメリット④インフレのリスクがある
貯蓄型の生命保険は、長期固定金利制が採用されています。
それゆえ、加入後にインフレが進むと、解約返戻金や満期保険金として払われる金額が減少するリスクがあるのです。
これらのリスクを回避するのであれば、貯蓄型の生命保険のうち、利率変動タイプを選ぶことをおすすめします。
貯蓄型の生命保険が向いている方

続いて、貯蓄型の生命保険に向いている方の特徴を解説します。
➀支払った保険料を無駄にしたくない方
保険料を無駄にしたくない方は、満期を終了したあとに満期保険金が受け取れる、または解約したときに解約返戻金が受け取れる貯蓄型保険が向いているでしょう。
掛け捨て型保険の場合は、加入している間ずっと健康のまま満期をむかえても保険料が戻ってきません。
何十年間も保険料を支払ってきたけど使わずに満期をむかえると無駄に感じてしまう方もいるかもしれません。
②日ごろから貯蓄が苦手な方
将来のために貯蓄をしておいたほうが老後生活を安心できるのは分かっているけど、手元にあるお金を使ってしまい貯められない方は、貯蓄型保険が向いています。
保険に加入すると、支払方法がクレジットカードや口座振替などになるので自然と貯蓄ができてしまいます。
③老後資金のため貯蓄をしたい方
定年退職後の老後に向けて貯蓄をしておきたい方には向いている保険になるでしょう。
老後2,000万円問題の話がでている中、退職金や年金だけではとても不安です。
貯蓄型保険は契約期間満了時には満期保険金が受け取れ、途中で解約したときでも解約返戻金を受け取れるので、老後にまとまった資金を手にできます。
④貯蓄と保険をまとめたいと考えている方
貯蓄型の生命保険は、貯蓄と保険がセットになった保険商品なので、毎月の保険料を支払うだけで、どちらもカバーできてしまいます。
貯蓄と保険を分けるとお金の管理も煩雑になるので、1つにまとめてラクにしたいとお考えの方には、貯蓄型の生命保険が向いています。
⑤保険の見直しや乗り換えが面倒だと感じる方
貯蓄型の生命保険は、目的が明確であり、よほどの事情がない限り内容の見直しや乗り換えの必要はありません。
見直しや乗り換えを避けたい方は、貯蓄型の生命保険を選ぶとよいでしょう。
貯蓄型保険の選び方のポイント

最後に、貯蓄型保険を選ぶ際に気をつけておきたい4つのポイントを解説します。
ポイント①貯蓄型の生命保険の特徴を知る
まずは、貯蓄型の生命保険の仕組みやメリット・デメリットを整理しておきましょう。
そのうえで、掛け捨て型の生命保険のメリット・デメリットと比較すれば、選択肢の幅が広がり、よりご自身に合った保険を選ぶ助けとなります。
関連記事:生命保険の掛け捨てとは?特徴やメリット・デメリットを詳しく解説
ポイント②必要な保険を見極める
貯蓄型の生命保険の仕組みや特徴を咀嚼できたら、続いてどの種類の保険商品にするのかという点を吟味しましょう。
貯蓄型の生命保険は、目的やライフプランによっていくつかの種類があり、それぞれ特徴が大きく異なります。
たとえば、子どもの教育資金を目的とした学資保険や、老後の資産形成を目的とした個人年金保険などです。
まずは目的から逆算して、ご自身に合った保険商品を選択されてください。
【関連記事】
20代における保険の必要性と20代におすすめしたい保険
30代におすすめしたい保険の選び方を解説!必要性や加入率も確認
ポイント③保険金額を決める
貯蓄型の生命保険のどの種類に加入するのかの目途が立ったら、続いて保険金額を決めます。
保険金額が高ければ、それだけ月々の支払いもかさむため、家計とのバランスをみながらコースを決めることが肝要です。
ポイント④返戻率を確認する
貯蓄型の生命保険は、解約返戻金を受け取れますが、解約のタイミングによっては受け取れる金額が、これまで支払った金額の総計を下回る場合があります。
そのため、解約の時期や受け取れる金額の違い、計算方法を保険会社の営業担当者にしっかりと相談しておきましょう。
関連記事:生命保険を解約せざるを得なくなったら?最適なタイミングを解説
貯蓄型保険の特徴を理解して将来の資金を考えよう

いかがでしたか。
生命保険と言ってもさまざまな種類や特徴があります。
今回は貯蓄型保険の特徴やメリット・デメリットについて解説をしました。
貯蓄型保険は、万が一の保障はもちろんですが、契約満期となれば満期保険金が受け取れます。
また、途中で解約をしてしまってもタイミングによっては解約返戻金が受け取れるので、老後にまとまった資金が手に入り自由に活用できます。
ほけんスマイルでは、「保険の新規加入」はもちろん、「契約中の保険の見直し」または「家計の相談」「将来の貯蓄」に対して、訪問やオンラインで対応をしております。
兵庫県で保険を見直すならほけんスマイルへいつでもお気軽にご相談ください。
近くの店舗の予約はこちらから
※オンラインでの保険相談をご希望される方は以下のページをご覧ください。 オンライン保険相談についてはこちら
お客様の声

親身になって必要な
保険を教えてくれました!
30代男性保険見直し生命保険
30代に入り家族も増え、真剣に将来のことを考え始めたところでした。そんな時、友人に勧められ訪れました。私のライフステージに合わせた生命保険の提案をしてもらえました。特に子供の教育資金や将来のリスク管理に関するアドバイスが具体的で、非常に参考になりました。ほけんスマイルの方々は知識が豊富で、安心して相談に乗ってもらえる環境が整っていました。今後も家族の安全を守るために、ほけんスマイルと長く関わっていくつもりです。

新規で生命保険に加入して、
未来への安心を手に入れました!
20代女性新規加入生命保険
保険のことは難しくてよくわからなかったのですが、ほけんスマイルのスタッフさんがとても親身になってくれて、自分にとって最適な保険プランを提案してくれました。
私でも理解しやすいように、細かいポイントまで説明してくれたので、安心して加入することができました。これで万が一の時も安心です。

医療保険への新規加入で
安心を得ました!
30代女性保険見直し医療保険
医療保険を見直したいと思いつつ、どの代理店に相談すれば良いのか分からなかったのですが、知人に勧められたほけんスマイルで相談して大正解でした。
30代という節目での見直しに対して、具体的で実用的なアドバイスを受けることができ、保険内容も大幅に改善されました。